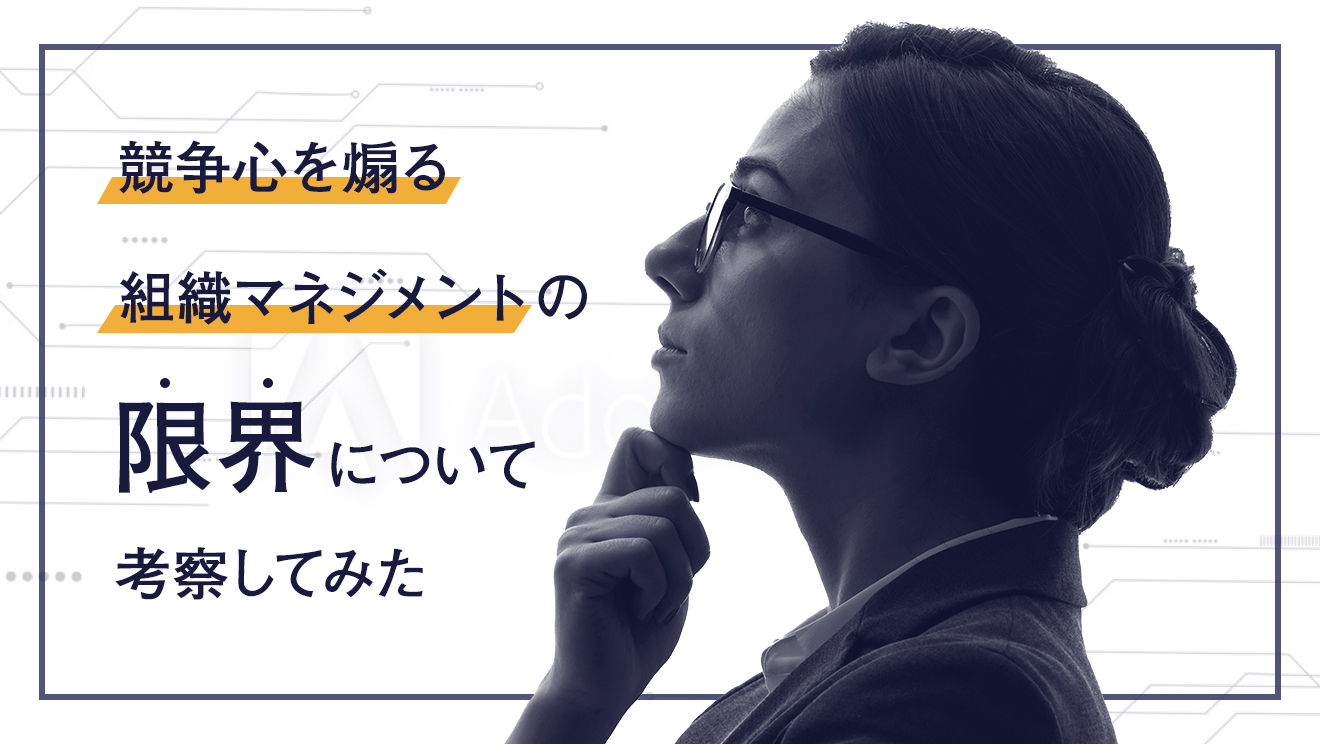人事部門を企業の“競争優位の源泉”にするための3つのアクション

「人的資本経営(人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方)」が注目されている近年。
人材に関する注目度がますます高まる中で、企業の中でも、人的資本に関する課題が認識され始めている。
デジタル化や脱炭素化、コロナ禍における人々の意識の変化など、経営戦略と人材戦略の連動を難しくする経営環境の変化が顕在化するにつれ、非財務情報の中核に位置する「人的資本」が、実際の経営でも課題としての重みを増してきている。
しかし、「人が資本だ」とはわかりつつも、今なお多くの企業では、「人事部門は労務や福利厚生や入社オリエンテーションなどの事務管理を行うような裏方だ」と考えている経営陣や社員が多い。
もちろん、事務管理は必要だが、組織に大きな付加価値をもたらすことは少ない。
HR総研により「人事の課題とキャリアに関するアンケート調査」でも人事部門のパフォーマンスについて質問したところ、「50~70点未満」(39%)がトップで、「30~50点未満」(34%)が多く、「30点未満」が11%も存在する。人事部門の評価はやはり辛口なのが現状だ。
どのようにすれば、人事部門が企業の競争優位の源泉へと進化できるのだろうか。本記事ではどんな手段とロードマップがあるのか考えてみたい。
目次
1.人事部門のケイパビリティの5つのレベル
人事部門が管理部門ではなく、価値提供部門として成長するためには、具体的にはどのようなロードマップがあるのだろうか。
私は、大きく人事部門を5つのケイパビリティ(企業の組織的能力、強み)のレベルで分けて考えている。
① 目の前の業務を回すのが精一杯で、現場の御用聞きになっている
多くの中小企業の人事部門はこの段階ではないだろうか。
この段階の人事はノンコア業務(利益に直接つながらない業務)とコア業務(利益に直結する業務)を切り分けることができず、特に採用の日程調整等で1日が消化されることが多い。
当然ながら、現場の採用ニーズに応えることが難しく、すべて現場からの提案ベースで人事が動くことが多いため、現場からの信頼度も当然ながら低い状態にある。
②滞りなく業務を進めているが「採用部」止まり
レベル2の段階は、目の前の定型業務を滞りなく進めている状態。いわば人事のインフラを回している段階だと言える。
しかし、「人事部」ではなく、「採用部」「労務部」「教育部」といった特定の人事ファンクションのみを行っていることが多い。
例えば「採用」に焦点を当てた場合、採用媒体や転職エージェントなど、採用費用を投下したフロー型の採用に依存していることが多く、自社ならではの採用ブランディングを中心とした創意工夫が欠けている段階とも言える。
③課題解決型「人事部」
レベル3の段階は「人事領域の広範囲を自社内で抱えており、なおかつ潤沢な人事リソースが整っている企業」に多い。
こうした企業は、課題解決型の人事機能をもち、1〜2年程度のスパンで現場のニーズを先回りし、採用・育成・評価・配置・人材開発・組織開発などの一貫性のある施策を展開できている。
この段階になると、人事部門全体がプレゼンス(存在感、影響力)をもち始め、現場が人事に協力的になり、同時に社内からも注目も浴びるようになる。
④経営と人事の一体化、「人事部」から「戦略人事」へ
レベル4の段階は、「CHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)」が設置されることが多く、より人事に戦略性が増すことが多い。
この段階は、経営戦略と人材戦略を連動させるため、全社的な経営的課題及び組織・人材的課題を経営トップとCHROを中心に対話を深め、課題を抽出し、両戦略を連動させていることが大きな特徴である。
人材に関する取り組みは、息の長いものとなる。その意味でも、5年先の組織図から逆算した人材戦略の提示と優先順位を付け、その効果を見極めて改善を重ねていく絶え間ない試行錯誤が求められる。
この試行錯誤の先に、変数が多い組織・人材領域に再現性が出てくるようになるのだ。
⑤強固なカルチャーが醸成され、人が「育つ」磁場になる
レベル5の段階になると、その組織にしか滲み出せない強力なカルチャーが形成され、そのカルチャーが人を育て、なおかつ、人を引き寄せるようになる。
この強力なカルチャーは、部外者の理解をにわかには得られないような「奇怪なルール・哲学・ポリシー」が暗黙知で共有され、組織自体が強烈な個性を生む。やがて、他社が真似できない「模倣不可能な領域」にまで進化するのだ。
この段階は、CHROが設置されていることはもちろんだが、経営陣(特にCEO)が組織・人材ファーストの経営を行なっていることが特徴と言える。

2.組織に求められる次世代のCHROの役割とは
これまで人事部門の価値を再定義した上で、そのレベルや段階を考察してきたが、人事部門を企業の競争優位の源泉にするために、より一層重要性を増しているのは、やはり「CHRO」の存在だと言えよう。
そこで、この章ではこれからの次世代「CHRO」の役割について考察してみたい。
まず大前提として、CHROはCEOが全幅の信頼のおける一流のビジネスリーダーである必要がある。
伝統的な人事リーダーみたく、制度や仕組み、プロセスのことのみ考えるのではなく、企業の非連続な成長のために、自ら事業に関わり、どんどん外に出て現場と向き合い、全社の戦略的な方向に人事スペシャリストとして、イニシアチブを握る必要がある。
その上で、どのような役割及び能力が求められるのだろうか。私は欠かせられない点として、大きく3つあると考える。
①組織がうまく機能(循環)しているかを見極める直観力
私が考える「CHROに最も求められる能力」が、組織がうまく機能(循環)しているかを見極める直観力だ。組織の表層的課題ではなく、深奥的な根本課題の察知と、その突破口がどこに(どの人材に)あるのかを嗅ぎ分ける嗅覚が必要になる。
現代はHRテクノロジー(人事・労務の分野で使用するシステムやアプリケーション)が発達し、多数の組織エンゲージメントを可視化するツールが存在する。
しかし、人事リーダーがデータを深く理解し、本質を見抜いた分析と考察、さらにはそのデータを元にした現場との丁寧な対話を重ねているかはまだ改善の余地がある。
どれほどテクノロジーが発達しようと、データの分析結果を再解釈し、有益なアドバイスや戦略に変換するためには、有能な人事部門の専門家がいないと生まれないのだ。
②CEO及びCFOとの深い関係構築能力
CHROには、企業に存在する数ある役割・ポジションの中でも、特にCEO(Chief Executive Officer:最高経営責任者)とCFO(Chief Financial Officer:最高財務責任者)と深い信頼関係を構築する必要がある。
企業自体が組織や人材リテラシーを向上させる際は「CEOがどのくらい人材について高い意識を持っているか」が大きなポイントとなる。
しかし残念ながら、過去数十年の経営の定石により、短期業績にインパクトを与える売上や利益などの財務施策が最優先され、人材に関する取り組みは後回しになることが多い。
人材の鍵を握るのは、やはりCHROの存在だ。CHROには、CEOに自ら人的資本の価値を訴求し続け、さらに数字でも証明し続ける地道な活動と、CEOに真正面から意見を言う勇気が必要である。
一方、CFOは財務と人事を対等な立場のプレゼンスを築くためのキーマンだ。
CFOは高い数字能力と論理性など高いビジネススキルを有することが多いゆえに、CEOの最も近くにいる関係と言っても過言ではない。
CHROは対人スキルを有しているものの、定性的で直観型のタイプが多いため、CFOと密に関係を築こうとしないケースが意外と多い。
そのため、今後はCHROが戦略的な考え方を有し、財務的な意思決定の議論に加わるなど“CFOと密に連携すること”が、金融資本と人的資本の価値を同一のものとする「これからの人的資本経営」のために欠かせない一歩になる。
③事業インパクト志向とクリエイティブさ
「現場部門のビジネスパートナーたれ」
これは、いわゆる従来のCHROに、最も必要とされてきた観点である。各事業部門に寄り添い、ビジネスのパフォーマンスを最大化するために、人と組織の側面から支援する役割だ。
しかし、昨今のビジネスパートナーには、事業部門のリクエストに応えることだけではなく、彼らがまだ顕在化していないニーズを感知し先回り、事業に大きな影響を与えることがより一層求められる。
その影響力を発揮するには、事業に対する深い理解や、そのときどきの状況を正しく把握していること、現場に対して意味ある助言ができる高い見識が必要になる。

3.新たな人事のキャリアパス
次世代のCHROは非常にクリエイティブな要素が強く、事業に真にインパクトを与えられる存在である。
知的好奇心をもって、事業を深く理解し、かつ事業に積極的に越境しようとし、現場の中で誰が真に組織の命運を握る人材なのかをアジャイルで見極め、CEOとCFOに戦略的提言をトライアンドエラーを重ねながら実行していくことが理想である。
それでは、そう言った力を身に着けるためには、何が必要なのだろうか。
従来、「人事部門を事業に近づける」といった類の主張がされてきているものの、うまく機能しているケースは少ない。
これには、大きく2つの理由があると考える。まず1つ目は多くの企業で人事面に関する義務的な事務手続きが時間とエネルギーを奪ってしまっている傾向にあるからだ。
2つ目は、上記の事務管理的手続きに安住し、事業部門に進んで越境しようとする意欲も削がれてしまっているからだ。
したがって、事業面と人事面の戦略的な打ち手に明るい人材をパイプラインに用意する必要がある。その最も効果的なソリューションは、人事のリーダーを事業部に異動させ、事業部のリーダーを人事部に異動させることだ。
つまり、「交換留学」させること。この経験により、人事のリーダーたちは、事業理解と業績目標の臨場感、また抜擢候補となる組織の要となる人材の早期発見といった視点を得ることができる。
一方、事業部のリーダーたちは、適切な人材を採用することの重要性と評価、組織カルチャーなど、人事のサイクルやリズムを体感覚で知ることができる。
しかし、このような「変革」と言ってもいい動きは、やはり取締役会と経営幹部の同意のもと、CEOが中心になって押し進める必要がある。
なぜなら、財務中心のこれまでの経営の定石から人事部門の再構築が重要であることや、人的資本の経営スタイルへ変わるための意義と意味を説得できるのは、やはりCEOしかいないからである。
長年、過小評価されてきた人事部門のポテンシャルを開放するのは、それほど大きなエネルギーを要するプロジェクトだが、やり切った先に得られる果実も同時に大きいものになる。
4.人事部門をバリューアップさせる3つのアクション
この章では、明日から始められる人事部門をバリューアップさせるためのアクションについて考えてみたい。下記に3つ紹介する。
①CEOと全社的な経営課題・組織課題について週次で対話をする
人事部門をバリューアップさせるためにはCEO、できればCFO(もしくはそれに準ずる経営幹部)の同席の下、全社的経営課題や組織課題について理解と議論を深める必要がある。
それぞれ三者の立場から考察する経営課題の持ち寄りと「なぜそう判断するのか」という議論は非常に価値の高いものとなる。
このアクションを行うことで、財務と人事が密接にリンクし、お互いが弱点を補うことが可能になる。
私が取締役CHROを務める、医療福祉事業のあるソーシャルベンチャーは取締役四名と毎週土曜日の午前中に対話の時間を設けている。いわば「朝活」である。他の会議との一番の違いはアジェンダがないことである。しかし、目的はただ一つでお互いの立場から考察した全社的イシューを持ち寄り、対話と理解を重ねることだ。通常の会議はネクストアクションが提示され、タスクリストに追加され、行動を定点観測するのが一般的だが、この会議は最も重要でインパクトが大きい長期的な時間軸の中で実現できるテーマについて語り合う。対話と理解を重ねることが目的なので、解釈をし評価及び否定をする場ではないことが大事である。
この場があることで、定量的な短期的財務テーマと定性的な長期的人事テーマがリンクする。組織や人事のリテラシーや感性が乏しい役員でも、「次、伸びてきそうな人材は誰なの?」という会話が日常的に発生し、その人材は役員直下の横断プロジェクトにアサインするなどアジャイルな抜擢が生まれている。
②組織の命運を握る「要となる人材」を早期に見つけ、関与する
人事リーダーが現場にもっと越境していくべきだと指摘したが、それは組織の命運を握る要人材を現場で見つけるために実践するのがおすすめである。
その際、事業部長クラスの人材に「今、誰が急成長している人材か」「今、誰が注目株の人材か」「今、誰に経営資源を投下し、成長のための機会と環境を与えるか」「今、誰にタフアサイメント(スキルアップのために、あえてハードルの高い課題や仕事を割り振ること)したら面白い変化が起きそうか」などを事前にヒアリングした上で、実際に現場を見てみるといい。
その後で、タテの1on1では吸い上げきれない情報や状態に人事が介入することで、ナナメからの視点から1on1で事業部長クラスに報告と提案をすると非常に価値がある。
③1週間現場の仕事を体験してみる
①②のアクションをする際、「事業がわかったようでわからなかった」ということに危機感を感じる人事担当者は多い。
それは何も悪いことではなく、現状認識という意味で非常に大事である。もしそのように感じたら、1週間で本業の20%ほど時間をあて、現場でインターンシップをすることをおすすめする。
直接現場の業務を実践してみたり、一緒に顧客先に訪問したり、事業部内での会議にオブザーブ(立ち会うこと:慣れたらファシリテーションするとなおいい)したりすれば、事業への理解が深まるだろう。
以上、人事部門を企業の競争優位の源泉とするために明日からでも実践できることを紹介した。
人材に関連する取り組みはやはり息の長いものであり、「ステップ・バイ・ステップ」が何より大事になる。
組織に関しても大きなビジョンを持ちつつ、スモールのアクションを大事にし、組織のポテンシャルが日に日に感じられるようになることを願っている。